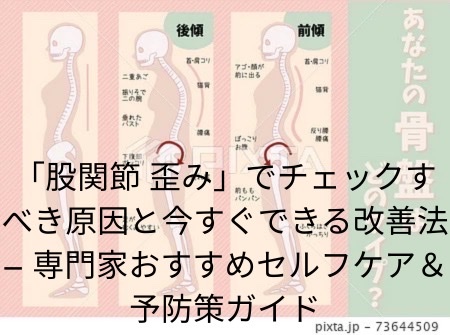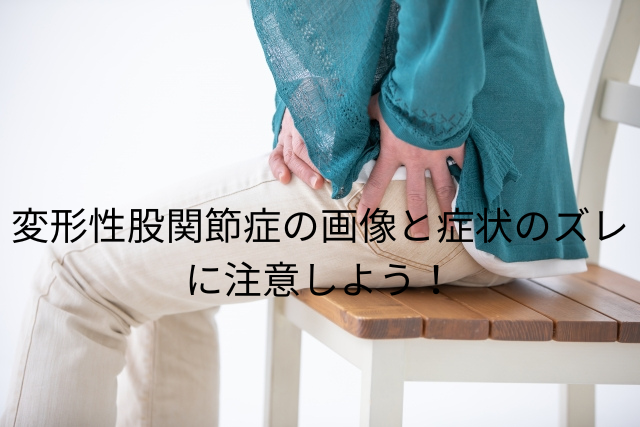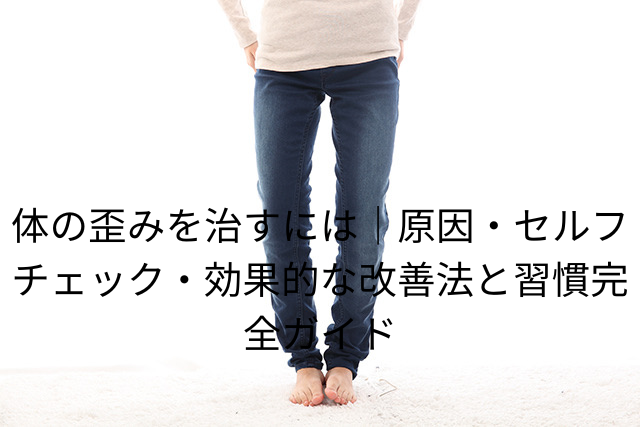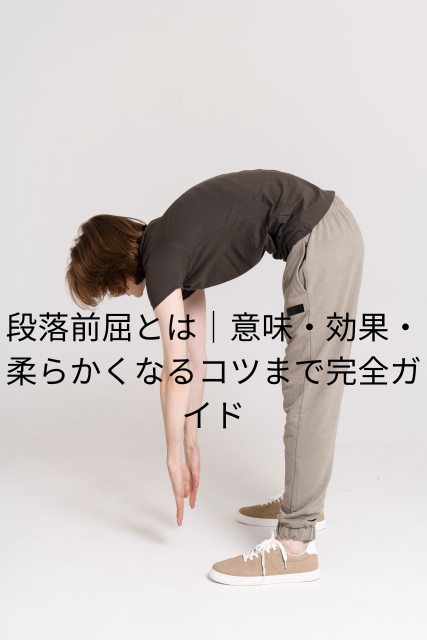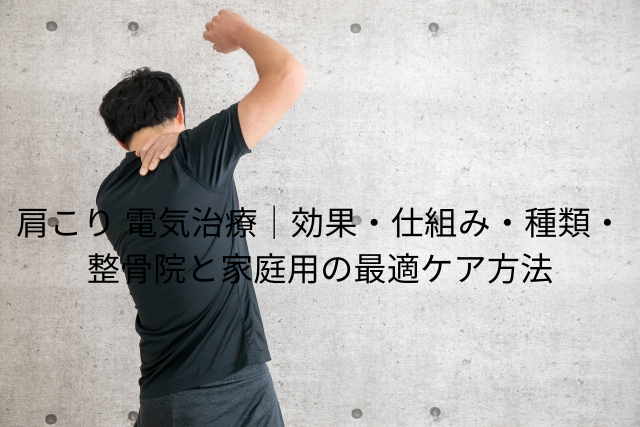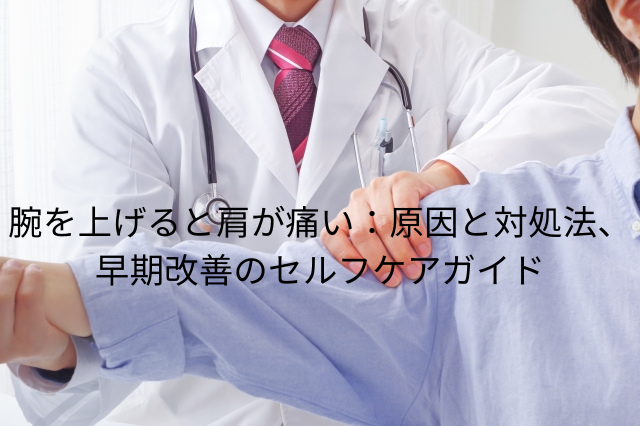

| . 腕を上げると肩が痛いと感じるとき、最初に確認すべきこと | ・痛む角度・時間帯(最初、途中、最大挙上で痛むか) ・痛みの性質(ズキズキ・鋭い痛み・だるさ) ・受傷歴・日常動作・姿勢習慣の有無 |
| 2. 考えられる主な原因(疾患・状態)とその特徴 | ・肩関節周囲炎(四十肩・五十肩) ・腱板損傷(部分断裂・完全断裂) ・肩峰下インピンジメント症候群 ・石灰沈着性腱板炎 ・上腕二頭筋長頭腱炎 ・頚椎由来(神経根症・頚椎症) ・その他(肩関節唇損傷、脱臼など) |
| 3. セルフチェック法・痛みの見分け方 | ・挙上角度別チェック(30°/60°/90°など) ・動作で試すチェック(外旋/内旋・前挙上 vs 外挙上) ・痛み再現テスト(インピンジメント徴候、Neerテスト、Hawkinsなど) ・可動域制限や筋力低下の確認 |
| 4. 初期対応・セルフケア・生活でできる対処法 | ・安静と動かすバランス(痛みが強い時 vs 軽くなった時) ・アイシング or 温め(炎症期 vs 慢性期) ・ストレッチ・関節可動域訓練・肩甲骨運動 ・筋力強化(肩甲骨まわり、小さな負荷から) ・姿勢改善・肩に負担をかけない動作指導 |
| 5. 受診の目安・医療機関での主な治療法 | ・「ここまで来たら受診を検討」サイン(夜間痛・可動域ゼロ・筋力消失など) ・整形外科での診断(レントゲン・エコー・MRI) ・保存療法(リハビリ・理学療法・注射療法) ・手術療法(腱板断裂修復、石灰除去、関節鏡など) ・治療期間・回復までの流れ |
1.腕を上げると肩が痛いと感じるとき、最初に確認すべきこと

「腕を上げると肩が痛い…」と感じたとき、まず確認したいのが“どんな動きで”“どんなタイミングで”痛みが出ているかです。単なる筋肉のこわばりなのか、肩関節そのもののトラブルなのかを見分けるための大事なポイントになります。
痛む角度や時間帯をチェックしよう
たとえば、腕を上げ始めた瞬間に痛む人もいれば、途中で引っかかるような痛みを感じる人もいます。さらに、腕を真上まで上げたときだけズキッとくるというケースもあります。
これは、痛みの出る角度によって原因が異なると考えられており、肩の動きを妨げる筋肉や腱の状態を知る手がかりになるそうです(引用元:疼痛.jp、中嶋整形外科クリニック、国立長寿医療研究センター)。
また、「朝起きた直後に痛い」「夜にうずく」といった時間帯も重要です。夜間にズキズキ痛む場合は、炎症を起こしている可能性があるとも言われています。
痛みの性質を感じ取る
「ズキズキ」「鋭くピリッとする」「だるく重い」など、痛みの種類を言葉で表すと原因の手がかりが見えやすくなります。
たとえば、ズキズキとした持続的な痛みは炎症に関連することが多く、動かした瞬間だけ痛む鋭い痛みは腱や筋肉の損傷が疑われることもあります。
反対に、鈍いだるさが続く場合は、長時間同じ姿勢でいることで肩周囲の血流が滞っているケースも少なくありません。
痛みの特徴を自分なりに言葉にしておくと、後で専門家に相談するときもスムーズです。
日常動作や姿勢のクセにも注意
肩の痛みは、姿勢や生活動作の積み重ねが影響していることも多いです。
例えば、スマートフォンを長時間見続ける姿勢や、デスクワークで肩をすくめたままの状態が続くと、肩甲骨の動きが制限されやすくなると言われています。
また、過去に転倒して肩を打ったり、スポーツで腕を酷使した経験がある場合は、腱や靭帯の損傷が関係しているケースもあります。
一見関係なさそうな「日常のクセ」や「過去のケガ」も、実は痛みの原因につながっていることがあるため、思い当たることがあればメモしておくとよいでしょう。
自分の体のサインを見逃さない
肩の痛みは、放置すると動かしづらくなったり、着替えなどの生活動作に支障が出ることもあります。
「そのうち良くなるだろう」と我慢せず、痛みが続くときは早めに専門家に相談することが大切です。
特に夜に痛みが強くなる場合や、腕が真上まで上がらない状態が続くときは、整形外科などで検査を受けておくと安心です。
#肩の痛み #腕を上げると痛い #肩甲骨の動き #姿勢改善 #セルフチェック
2.考えられる主な原因(疾患・状態)とその特徴

腕を上げると肩が痛いとき、原因は一つではありません。年齢や生活習慣、使いすぎなど、さまざまな要素が関係していることが多いと言われています。ここでは、代表的な疾患や状態をいくつか紹介します。
肩関節周囲炎(四十肩・五十肩)
「腕を動かすと痛い」「背中に手が回らない」などの症状が特徴的です。肩関節を包む袋(関節包)や腱が炎症を起こし、動かすたびに痛みを感じるようになります。
初期はズキズキとした痛みが強く、次第に動かしづらさ(拘縮)が出てくることがあるそうです。特に夜間の痛みで眠れないという人も少なくありません。
中高年に多く見られ、自然経過で改善していく場合もあると言われていますが、痛みが強い時期は無理せず、専門家のアドバイスを受けながら肩の動きを保つことが大切です(引用元:横浜町田関節脊椎病院、中嶋整形外科クリニック)。
腱板損傷(部分断裂・完全断裂)
肩の中には「腱板」と呼ばれる筋肉の腱の集まりがあり、腕を上げたり回したりする際に重要な働きをしています。
この腱板が切れたり、擦り切れたりすることで痛みや力の入りにくさが生じるとされています。転倒やスポーツでの外傷だけでなく、加齢による変性でも起こることがあるそうです。
症状としては「腕を横に上げると痛い」「上げきれない」「夜にズキッと痛む」といったものがよく見られます。早めにエコーやMRI検査を行うことで、損傷の程度を確認できるといわれています(引用元:内閣府国民生活センター、霞ヶ浦医療センター)。
肩峰下インピンジメント症候群
肩を上げるときに腱板や滑液包が骨にぶつかり、痛みを感じる状態を「インピンジメント」と呼びます。
特に「90度前後で引っかかるような痛み」が特徴的で、野球やテニスなど、腕を繰り返し上げる動作が多い人に見られることがあるそうです。
放置すると腱板に炎症が広がることもあるため、肩甲骨周りの動きを整えるストレッチや、負担を減らす姿勢改善が勧められています(引用元:疼痛.jp、入谷整形外科)。
石灰沈着性腱板炎・上腕二頭筋長頭腱炎
腱の中に石灰がたまることで突然の強い痛みを引き起こすのが「石灰沈着性腱板炎」です。何もしていないのに急に肩が上がらなくなる、夜にズキッと痛むといった症状が多いようです。
一方、上腕二頭筋長頭腱炎は、腕を曲げたり捻ったりする動作で肩の前側に痛みを感じるのが特徴です。いずれも炎症によって痛みが強く出ることがあり、安静と炎症コントロールが重要だとされています(引用元:シンセルクリニック)。
頚椎由来(神経根症・頚椎症)
肩自体ではなく、首(頚椎)からくる神経の圧迫によって肩や腕に痛みやしびれを感じることもあります。
この場合、腕を上げなくても痛みや違和感が続くことがあり、肩こりと区別がつきにくいケースも少なくありません。
長時間のスマホ操作やデスクワークによる姿勢の乱れが関係していることもあるため、頚椎の状態を含めてチェックすることが推奨されています(引用元:足立慶友整形外科、倉石整形外科クリニック)。
その他の原因
スポーツや転倒で起こる「肩関節唇損傷」や「脱臼」なども、腕を上げるときの痛みの原因になることがあります。
これらは外傷性の要素が強く、可動域の制限や不安定感を伴うことが多いため、早めの検査がすすめられています。
#肩の痛み #腕が上がらない #腱板損傷 #五十肩 #インピンジメント
3.セルフチェック法で「腕を上げると肩が痛い」を見極める

腕を上げると肩が痛いと感じるとき、自分でできる簡単なチェックをやっておくと、後で専門家に説明しやすくなります。ここでは “どの角度で痛むか”“どの動作で痛むか” を見分ける手順を紹介しますね。
挙上角度別チェック(30°/60°/90°などで確認)
まずは腕をゆっくりと上げて、30度、60度、90度の各段階で「痛みの出方」を感じてみてください。
-
30度あたりで痛みが出るなら、最初の動きでの腱や滑液包の圧迫が関係している可能性があります。
-
60度近辺で痛むなら、肩峰下インピンジメント症候群などが疑われるケースがあります(これは、腱や滑液包が骨とぶつかる動きと重なる角度だからです)。
-
90度近くで痛みが強まるなら、腱板や肩峰の形状、肩甲骨の動き制限が影響しているかもしれません。
このように角度を区切って痛みを確認することで、「どの位置でつっかえるか」がヒントになります。
外旋/内旋・前挙上 vs 外挙上でのチェック
痛みの性質をさらに絞るには、腕をひねる動作も試してみましょう。例えば:
-
腕を外に回す(外旋)・内に回す(内旋)動作で違和感や痛みがないか。
-
前方に上げる(前挙上)と、側方に上げる(外挙上)を比べてみて、どちらの方向でより痛むか。
これによって、関わる筋肉や腱、滑液包の位置関係がある程度想定できます。「前方だけ痛い」「横方向を持ち上げると痛みが鋭くなる」などの違いを覚えておくといいです。
痛み再現テスト(インピンジメント徴候、Neerテスト、Hawkinsテストなど)
ある程度安全に試せるテストもあります。ただし無理は禁物。痛みが激しいときは控えてください。代表的なものを挙げます:
-
Neerテスト:肩を内旋させた状態で、他動的に前方に挙上して痛みが誘発されるか確認する方法。陽性ならインピンジメントが関係している可能性が高いと言われています。引用元:PhysioApproach「ニアーテスト/ホーキンステスト」 physioapproach.com
-
Hawkins(ホーキン)テスト:肩を90度屈曲・肘を90度曲げた状態から、肩を内旋させて痛みが出るかを試します。痛みがあるなら、肩峰下での腱板や滑液包の圧迫が疑われます。引用元:forphysicaltherapist「肩関節の徒手検査法まとめ」 forphysicaltherapist.com
-
Painful Arc(ペインフルアークサイン):腕を側方に上げていき、だいたい60~120度くらいの間で痛みが出るなら陽性とされ、インピンジメントや腱板に負荷がかかっている可能性があります。引用元:1post「整形外科的テスト 肩関節」 POST
これらのテストはあくまで“可能性を探る”ものなので、陰性だったから完全に否定できるわけではありません。
可動域制限と筋力低下の確認
最後に、普段の動きで「上がらない」「力が入らない」と感じるかどうかをチェックします。たとえば:
-
肩を上げようとして途中で止まる、またはそれ以上上がらない(可動域制限)。
-
腕を支えたまま少し力をかけてみたとき、力が入りづらい・ふらつく(筋力低下の可能性)。
-
肩を挙げたときゴリゴリ・ガクンと音がする、引っかかるような違和感を感じる。
こうした所見を自分でメモしておくと、病院や施術者に説明するときに役立ちます。可動域の基準や評価法については、整形・リハビリ分野でのゴニオメーター使用例も紹介されています。引用元:関節可動域測定方法(坂井メディカル) 坂井メドレー
これら一連のセルフチェックを通して、「どの角度で痛むか」「どの動きで痛むか」「可動域や筋力の異常があるか」を整理できます。もちろん自己判断には限界があるので、痛みが強い・長引く場合は専門家に相談することが大切です。
(ハッシュタグまとめ)
#肩のセルフチェック #腕を上げて痛い #インピンジメントテスト #肩可動域 #肩腱板チェック
4.初期対応とセルフケアで「腕を上げると肩が痛い」を和らげる

肩が痛いとき、「何もしないで安静」だけではかえって動かなくなってしまうことがあります。一方で無理に動かすのも逆効果。痛みの強さに応じて「休む時期」と「動かす時期」のバランスを取ることが大事と言われています。
安静と動かすバランス(痛みが強い時 vs 軽くなった時)
痛みが非常に強くて動かすだけで鋭い痛みが走るような時期は、無理をせず安静を優先させることが基本です。石灰沈着性腱板炎などでは、急性期に三角巾で腕を固定して負担を軽くする方法が紹介されています(引用元:石灰沈着性腱板炎の記事)seikei-mori.com
ただし、痛みが少し落ち着いてきた段階では、軽い動きから徐々に肩を動かすことがむしろ改善につながることも言われています。いわゆる “安静期を過ごした後の可動域維持・回復期” に、無理のない動かし方を取り入れていくのが自然な流れです。
アイシング or 温め(炎症期 vs 慢性期)
痛みが強い「炎症期」には、冷やすことで腫れや痛みを抑えることが有効とされます。氷嚢や冷却パックを使い、15分程度を目安に冷やすのが一般的な方法です(引用元:石灰沈着性腱板炎の記事)seikei-mori.com
一方、炎症が落ち着き、痛みが和らぎ始めた「慢性期」には、温めることで血流を改善し、硬くなった筋肉や関節をほぐすのが望ましいとされています。温熱療法やぬるめのお風呂で温める方法が用いられることもあります。
ストレッチ・可動域訓練・肩甲骨運動
肩関節を柔軟に保つためには、ストレッチや可動域訓練が不可欠です。急性期を過ぎれば、コッドマン体操(振り子運動)が比較的負担が少なく始められる方法として紹介されています。seikei-mori.com+1
また、タオルを使ったストレッチや壁を使った「フィンガーウォール」運動も肩の可動域を少しずつ広げる助けになると言われています(引用元:可動域制限解消コラム)札幌ひざのセルクリニック|変形性膝関節症・手術しない膝治療
さらに、肩甲骨まわりを動かすストレッチ(肩甲骨を寄せる/開く運動など)を取り入れることで、肩関節の動きを支える土台を整えることができます。MELOS(メロス)+1
筋力強化(肩甲骨まわり、小さな負荷から)
可動域を確保した後は、筋力をつけて肩を支える力を養うことが重要です。特に肩甲骨まわりの筋肉(ローテーターカフ群、僧帽筋、菱形筋など)を、小さな負荷から徐々に鍛えていくのがセオリーとされています。人形町整形外科ペイン•リハビリクリニック(整形外科•痛み専門)+1
たとえば、ゴムバンドを軽く引っ張る運動(抵抗バンドトレーニング)で、外旋・内旋運動をゆっくり行う方法がよく紹介されています。無理せず、痛みがない範囲でじわじわ筋力をつけていくことが肝要だと言われています。リペアセルクリニック大阪院
姿勢改善・肩に負担をかけない動作指導
日頃の姿勢や動作が肩痛のもとになっていることは少なくありません。猫背や巻き肩、前傾姿勢は肩の前方に負荷を偏らせることがあると言われています。CBC web〖CBC公式ホームページ〗 | CBCテレビ・CBCラジオ+2デサント+2
例えば、スマホを見るときに頭を前に突き出さず、画面を目の高さに近づける・肘をテーブルに支えるなど、肩へのストレスを軽減する工夫を取り入れてみてください。
また、重い物を持つときは腕全体ではなく体幹を使って持つなど、「腕だけでがんばらない」動作を意識することも効果的だと言われています。
これらのセルフケア・生活改善を組み合わせることで、痛みの軽減や再発予防につなげる可能性があります。ただし、痛みが長引く・夜間痛が強い・腕がほとんど上がらないという状態が続く場合は、早めに専門家に相談することをおすすめします。
(ハッシュタグまとめ)
#肩セルフケア #肩ストレッチ #肩筋力強化 #姿勢改善 #初期対応
5.受診の目安と診察を検討すべきサイン
 腕を上げると肩が痛いという状態で、「そろそろ病院へ行ったほうがいいのかな?」と悩む方も多いでしょう。以下のようなサインがあれば、整形外科や専門医のもとで検査を受けることを検討する基準とされています。
腕を上げると肩が痛いという状態で、「そろそろ病院へ行ったほうがいいのかな?」と悩む方も多いでしょう。以下のようなサインがあれば、整形外科や専門医のもとで検査を受けることを検討する基準とされています。
「ここまで来たら受診を検討」すべきサイン
-
夜間痛が強く、睡眠を妨げられるようになったときは、炎症が強かったり組織の損傷がある可能性があると言われています。
-
可動域がほとんどゼロになり、腕を上げようとしても全く動かせない状態が続くとき。
-
筋力が明らかに低下し、腕を支えられない・力を入れられないと感じるとき。
-
痛みが1〜数週間以上続いて改善傾向が見られない、あるいは段階的に悪化しているようなとき。
-
日常生活に支障が出始めたとき(着替えができない、洗髪がつらいなど)。
四十肩・五十肩のケースでは、痛みや拘縮(動かしにくさ)が現れてから1か月以内の早期受診を推奨する見解もあります(引用元:Doctors File「発症から1か月以内で相談を」) ドクターズ・ファイル
また、痛み・動かしにくさが1週間以上続く場合は整形外科での詳しい検査を勧めるという報告もあります(引用元:大川整形外科サイト) okawa-seikei.com
整形外科での診断方法
病院を受診すると、まず問診・触診によって痛みの部位や動作の再現性を調べたうえで、以下のような画像検査を組み合わせて診断が進められることが一般的と言われています。
レントゲン・エコー・MRI検査
-
レントゲン(X線)検査:主に骨構造の異常(骨折・骨棘・肩関節変形など)を確認する目的で使われます。ただし、腱や軟部組織(腱板など)は写らないため、直接の損傷は確認できないことが多いです(引用元:MUTO整形ガイド) muto-seikei.com
-
超音波検査(エコー):腱板や腱・滑液包の炎症をリアルタイムで調べられ、比較的手軽に実施できる検査手法と言われています(引用元:明鉄病院診療案内) 名鉄病院
-
MRI検査:腱板損傷・断裂の有無、範囲、関節包・滑液包・周辺軟部組織の状態を詳しく見るためによく使われます(引用元:MUTO整形ガイド、腱板損傷診療解説) muto-seikei.com+1
これらの検査結果をもとに、「肩関節周囲炎」「腱板損傷」「インピンジメント」「石灰性炎症」など、疑われる原因を絞っていく流れが多いようです。
保存療法とリハビリ・注射療法
多くの肩の痛みでは、最初に行われるのが保存的なアプローチです。症状の程度や診断結果によって、以下のような方法が採られることが多いと言われています。
保存療法(非手術的治療)
-
リハビリテーション/理学療法:可動域訓練、筋力強化、ストレッチ、肩甲骨運動などが段階的に行われます。
-
注射療法:痛みが強い時には、ステロイド注射や局所麻酔、エコーガイド下でのハイドロリリース(生理食塩水などで癒着をはがす注射)などを併用するケースがあります(引用元:明鉄病院、腱板損傷治療法) 名鉄病院+1
-
内服薬(消炎鎮痛剤):痛みや炎症を和らげる目的で使われることがあります(引用元:Akashi N Clinic 腱板損傷治し方) 中山クリニック
-
安静と段階的運動:痛みを誘発する動作を避けつつ、痛みが和らいだ段階で徐々に動かすことが推奨されています。
腱板損傷の場合、保存療法が原則で、3か月程度試して改善がなければ手術を検討するという流れが紹介されている医療情報もあります(引用元:Akashi N Clinic) 中山クリニック
手術療法と回復の流れ
保存療法で改善が見られない、または重度の断裂や機能障害が認められると判断された場合、手術療法が選択肢になります。
手術療法の種類
-
関節鏡視下腱板修復術:体を大きく切らず、カメラ(鏡視下)を使って断裂した腱板を元の骨付着部に縫い戻す方法が主流と言われています(引用元:溝口病院 腱板断裂 治療) 溝口外科整形外科病院
-
石灰除去術:石灰沈着性腱板炎が強く痛みを起こしている場合、石灰を除去する手術が行われることがあります。
-
複合的手術:断裂が広範囲、腱が引き延ばせない、筋肉萎縮があるケースでは、腱移植・補強術や人工関節を用いることもあると言われています(引用元:溝口病院、腱板断裂案内) 溝口外科整形外科病院
治療期間・回復までの流れ
術後は、まず 保護期(数週間~1か月程度)として動かさない・軽い可動域訓練からスタートすることが多いとされます。
その後 回復期・機能回復期 に入り、徐々に筋力訓練、日常動作訓練を進める流れです。完全な改善までには、状態にもよりますが数か月〜半年、あるいはそれ以上かかることもあると言われています。
また、手術後もリハビリを継続して機能を取り戻すことが、長期予後において重要であるとする見解もあります。
(ハッシュタグまとめ)
#肩の受診目安 #肩の検査方法 #肩保存療法 #肩手術法 #治療と回復の流れ